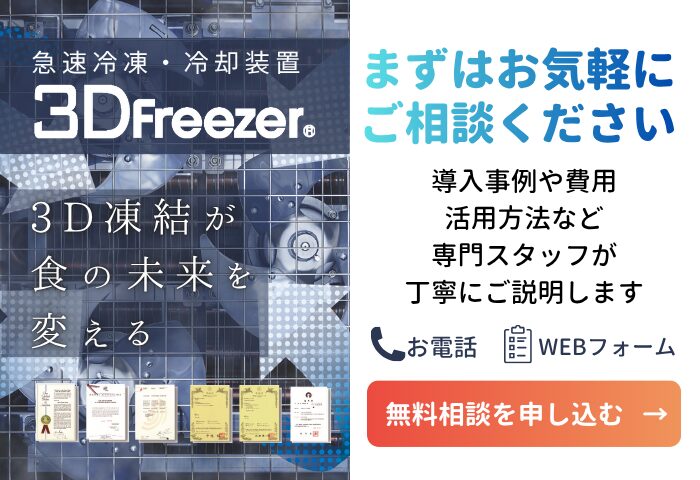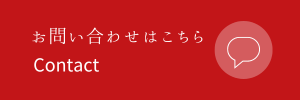「冷凍した刺身は、水っぽくて美味しくない」 「焼き魚にしたら、身がパサパサになってしまった」 「貝類を冷凍したら、身が縮んで硬くなってしまった」
寿司店、鮮魚店、水産加工業など、魚介類を扱うプロにとって、鮮度の維持は永遠の課題です。特に、魚介類は肉類以上に繊細で、冷凍による品質劣化が起こりやすい食材です。
しかし、それは「正しい冷凍方法」を知らない場合の話。獲れたての鮮度と旨味をそのまま閉じ込める「急速冷凍」の技術と、ちょっとしたコツを組み合わせることで、冷凍魚介類の品質は劇的に向上します。「冷凍はまずい」という常識は、もはや過去のものです。
この記事では、業務用急速冷凍機の専門メーカーであるKOGASUNが、魚介類の品質を最大限に保つためのプロの急速冷凍テクニックを、魚種や形態別に具体的に解説します。下処理から包装、解凍まで、この一手間が品質を大きく左右します。
Contents
なぜ魚介類は冷凍で品質が落ちやすいのか?
魚介類の品質が劣化する主な原因は3つあります。
1.細胞破壊によるドリップ: 魚の身は水分が多く、緩慢冷凍すると大きな氷の結晶が細胞膜を破壊し、解凍時に旨味成分を含んだドリップが大量に流出してしまいます。
2.脂肪の酸化: サバやイワシなどの青魚に多く含まれる不飽和脂肪酸は、空気に触れると非常に酸化しやすく、これが「冷凍焼け」や生臭い戻り臭の原因となります。
3.酵素による自己消化: 魚が死んだ後も、体内にある酵素は働き続け、身を分解していきます。これが鮮度低下の大きな原因です。
急速冷凍は、これらの問題を根本から解決します。素早く凍結させることで氷の結晶を小さく保ち、細胞破壊を抑制。さらに低温状態にすることで、脂肪の酸化や酵素の働きを遅らせることができるのです。


急速冷凍したマグロの刺身と、通常冷凍したマグロの刺身の比較写真。急速冷凍側は角が立ち、鮮やかな色でドリップがない。通常冷凍側は身がよれて、皿にドリップが出ている。
【種類別】魚介類の急速冷凍テクニック
魚介類と一口に言っても、その種類は様々です。ここでは代表的な魚介類について、最適な下処理と冷凍のコツを紹介します。
刺身・サク(マグロ、カツオ、サーモンなど)
•ポイント: 生で食べる刺身は、最も品質が問われます。色、食感、風味のすべてを維持することが目標です。
•下処理: キッチンペーパーで表面の水分(ドリップ)を丁寧に拭き取ります。特にカツオなどは血合いから水分が出やすいので念入りに行います。
•包装: 空気に触れさせないことが絶対条件です。吸水シート(ドリップシート)でサクを包み、その上から真空包装するのが最も理想的です。真空包装機がない場合は、ラップで隙間なく包み、さらにジッパー付き保存袋に入れて空気を抜きます。
•冷凍: 金属製のバットに乗せ、急速冷凍します。
切り身(サケ、サバ、タラなど)
•ポイント: 加熱調理用ですが、解凍後のパサつきを防ぎ、ふっくらとした食感を保つことが重要です。
•下処理: 軽く塩を振るか、白醤油や酒を薄く塗っておくと、浸透圧で余分な水分が抜け、ドリップを防ぐ効果があります(振り塩処理)。その後、出てきた水分をキッチンペーパーでしっかり拭き取ります。
•包装: 1切れずつラップでぴったりと包み、ジッパー付き保存袋に平らになるように入れて冷凍します。
丸魚(アジ、イワシ、サンマなど)
•ポイント: 内臓は傷みが早いため、できるだけ早く処理することが鮮度を保つ秘訣です。
•下処理: ウロコ、エラ、内臓を完全に取り除きます。腹の中をきれいに水洗いし、血合いもしっかりと掻き出します。その後、キッチンペーパーで腹の中まで含めて、全体の水分を徹底的に拭き取ります。
•包装: 1尾ずつラップで包み、ジッパー付き保存袋に入れて急速冷凍します。
貝類(ホタテ、カキ、アサリなど)
•ポイント: 貝類は加熱すると身が硬く縮みやすいのが難点。生の状態に近い食感をいかに保つかが鍵です。
•ホタテ(貝柱): 水分をよく拭き取り、1個ずつバラバラの状態で金属バットに並べて急速冷凍します(IQF凍結)。凍結後、ジッパー付き保存袋にまとめて保存します。
•カキ(むき身): 流水で優しく洗い、汚れを落とします。キッチンペーパーで水分を拭き取り、ホタテと同様にIQF凍結します。
•アサリ・シジミ(殻付き): 砂抜きを完璧に行い、殻の表面をよく洗います。水分を拭き取ってから、ジッパー付き保存袋に入れて急速冷凍します。凍ったまま調理に使えるので便利です。
甲殻類(エビ、カニ)
•ポイント: 黒変(ブラックタイガーの頭が黒くなるなど)や、解凍後の身のパサつき(身痩せ)を防ぐことが重要です。
•エビ: 背わたを取り、殻付きのまま、または殻を剥いてから冷凍します。水分をよく拭き取り、IQF凍結後に袋詰めします。
•カニ: 活きたカニは必ず締めてから、ボイルまたは蒸してから冷凍するのが基本です。殻のまま、または脚ごとに切り分け、乾燥しないようにグレーズ処理(後述)を施すか、ラップで厳重に包んで冷凍します。
プロの技!品質をさらに高めるテクニック
グレーズ処理
凍結した魚介類の表面に、薄い氷の膜を張る技術です。この氷の膜が、冷凍中の乾燥や酸化から食材を守るバリアの役割を果たします。カニやエビ、切り身など、むき出しの状態で冷凍する場合に非常に効果的です。
方法: 急速冷凍した食材を、一瞬だけ冷水にくぐらせ、すぐに冷凍庫に戻します。これを2〜3回繰り返すと、きれいな氷の膜ができます。
IQF(個別急速冷凍)
Individual Quick Freezingの略。ホタテやエビ、カットしたイカなどを、1個ずつバラバラの状態で急速冷凍する方法です。食材同士がくっつかないため、使う分だけ取り出せて非常に便利です。金属製のバットにクッキングシートを敷き、食材が重ならないように並べて急速冷凍します。
最高の状態で蘇らせる「解凍方法」
解凍は、冷凍と同じくらい品質を左右する重要な工程です。
•刺身・生食用: 氷水解凍が最適です。真空パックのまま氷水に浸け、低温で短時間に戻すことで、ドリップを最小限に抑え、鮮やかな色と食感を保ちます。
•加熱調理用: 冷蔵庫解凍が基本です。時間はかかりますが、低温でゆっくり解凍することで、ドリップの流出を抑えます。また、凍ったまま調理できる煮付けや汁物もあります。
絶対に避けるべきは、常温解凍と電子レンジ解凍です。品質を著しく損なう原因となります。
まとめ
魚介類の急速冷凍は、単なる保存技術ではありません。旬の美味しさを閉じ込め、フードロスを削減し、ビジネスの可能性を広げるための戦略的な技術です。
魚介類の品質を保つためのポイントを振り返りましょう。
•鮮度が命: 入手後はできるだけ早く、適切な下処理を施す。
•種類別の最適化: 魚種や形態に合わせた下処理と包装を行う。
•空気を遮断: 真空包装やグレーズ処理で、乾燥と酸化を徹底的に防ぐ。
•低温で解凍: 氷水解凍や冷蔵庫解凍で、ドリップの流出を抑える。
これらのポイントを実践することで、あなたの店の冷凍魚介類は、お客様を唸らせる一品に変わるはずです。
KOGASUNでは、マグロのサク、ウニ、アワビなど、これまで冷凍が難しいとされてきた様々な魚介類での凍結実績が豊富にあります。特に、乾燥を防ぐ当社の3Dフリーザー®は、魚介類の品質維持に絶大な効果を発揮します。
「自慢の魚が、どれほどの品質で冷凍できるか試してみたい」
そうお考えなら、ぜひ無料の冷凍テストをご利用ください。獲れたての感動を、冷凍で再現するお手伝いをいたします。