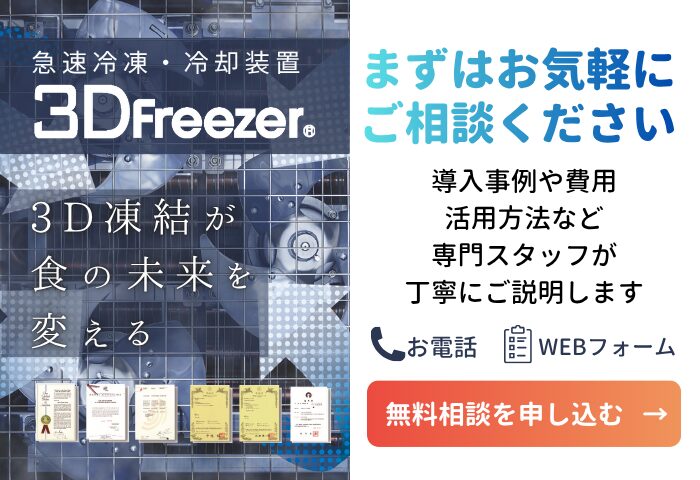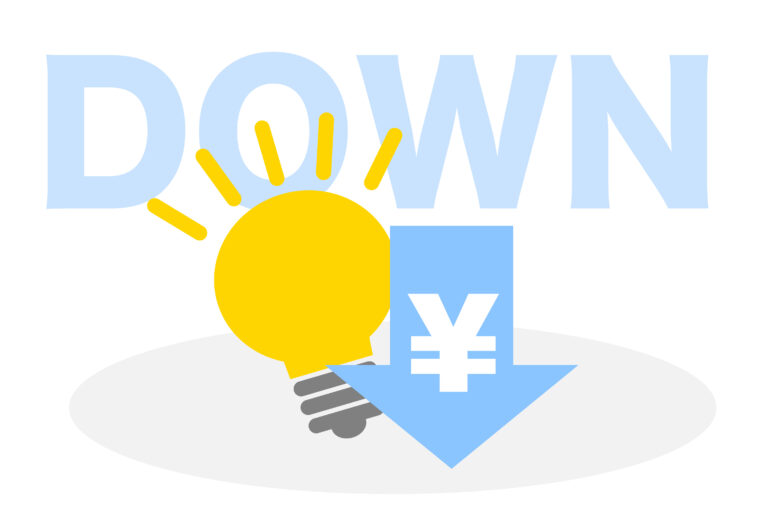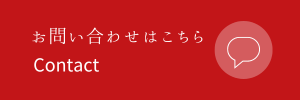「高価な急速冷凍機を導入したのに、期待したほど品質が良くならない」 「急速冷凍しても、結局ドリップが出てしまう」 「冷凍焼けして、食材がパサパサになってしまった」
急速冷凍機を導入したにもかかわらず、このような「失敗」に直面し、頭を抱えている方はいませんか?
急速冷凍は、食品の品質を高く維持できる画期的な技術ですが、残念ながら機械を導入さえすれば全てが解決する「魔法の箱」ではありません。 その性能を最大限に引き出すためには、正しい知識に基づいた適切な運用が不可欠です。
運用方法を間違えれば、せっかくの高性能な急速冷凍機も宝の持ち腐れとなり、期待した効果を得ることはできません。
この記事では、業務用急速冷凍機の専門メーカーであるKOGASUNが、これまでにお客様から寄せられた数多くの相談事例に基づき、急速冷凍でよくある5つの失敗パターンとその具体的な解決策を徹底解説します。失敗を防ぐためのチェックリストも用意しましたので、ぜひ自社の運用方法と照らし合わせてみてください。
Contents
急速冷凍でも失敗する?その原因とは
失敗の根本的な原因は、多くの場合、急速冷凍の「目的」を正しく理解していないことにあります。急速冷凍の目的は、「食品の細胞破壊を最小限に抑えるため、最大氷結晶生成温度帯(-1℃〜-5℃)をいかに速く通過させるか」という一点に尽きます。
これから紹介する5つの失敗事例は、すべてこの原則から外れた運用をしてしまった結果、引き起こされるものです。一つずつ見ていきましょう。
【失敗事例1】温度管理が不十分で品質が低下
ありがちな失敗: 「冷凍庫の温度設定を-30℃にしているから大丈夫」と思い込み、凍結完了までの時間を計測していない。
なぜ失敗するのか: 急速冷凍で最も重要なのは「設定温度」ではなく「凍結速度」です。たとえ設定温度が低くても、食材の量や入れ方によっては、中心部が凍結完了するまでに時間がかかり、結果的に緩慢冷凍と同じ状態になってしまいます。特に、熱いものを冷まさずに冷凍庫に入れるのは、庫内温度を上昇させ、他の食材の品質にも悪影響を及ぼす最悪のパターンです。
解決策
•食材の中心温度を計測する: 導入時に、主力食材の中心温度が最大氷結晶生成温度帯を30分以内に通過できているか、必ず計測・確認しましょう。
•粗熱をしっかり取る: 調理したての熱いものは、必ず粗熱を取ってから冷凍庫に入れます。ブラストチラーなどを併用するのが理想的です。
【失敗事例2】食材の前処理(下処理)を怠った
ありがちな失敗: 魚をウロコや内臓が付いたまま、野菜を泥が付いたまま冷凍してしまう。
なぜ失敗するのか: 食材に付着した水分や汚れは、品質劣化の大きな原因となります。
•水分: 表面の余分な水分は、霜の原因となり、冷凍効率を下げます。また、解凍時の臭みにも繋がります。
•汚れ・細菌: 汚れや細菌が付着したまま冷凍すると、解凍時に細菌が繁殖し、食中毒のリスクを高めます。
•酵素: 野菜や果物に含まれる酵素は、冷凍中もゆっくりと働き続け、色や食感、風味を劣化させます。これを「褐変(ブラウニング)」と呼びます。
解決策
•水分を拭き取る: 肉や魚の表面のドリップは、キッチンペーパーで丁寧に拭き取ります。
•洗浄・下処理: 魚はウロコ・エラ・内臓を取り除いてから、野菜は泥を洗い流してから冷凍します。
•ブランチング処理: 野菜や果物は、ブランチング(短時間の加熱処理)を行うことで酵素の働きを止め、色鮮やかさと食感を保つことができます。
【失敗事例3】冷凍機の処理能力を超えた量を投入
ありがちな失敗: 「まだスペースがあるから」と、冷凍庫内に隙間なく食材を詰め込んでしまう。
なぜ失敗するのか: 多くの急速冷凍機(特にエアブラスト方式)は、冷気を循環させることで食材を冷却します。食材を詰め込みすぎると、冷気の通り道がなくなり、庫内に温度ムラが発生します。風が当たらない場所の食材は凍結速度が著しく遅くなり、品質が大きく損なわれます。
解決策
•最大処理能力を守る: メーカーが定めた1回あたりの最大処理能力(kg)を必ず守りましょう。
•食材同士の間隔を空ける: 冷気が全体にいきわたるよう、食材と食材の間には必ず隙間を空けて配置します。
•複数回に分ける: 一度に冷凍したい量が多い場合は、面倒でも複数回に分けて冷凍しましょう。
【失敗事例4】包装・密閉が不十分で冷凍焼けが発生
ありがちな失敗: ラップで簡単に包んだだけ、あるいは蓋がしっかり閉まらない容器に入れて冷凍してしまう。
なぜ失敗するのか: 包装が不十分だと、食材が冷気に直接さらされ、表面の水分が昇華(個体から直接気体になる現象)して乾燥してしまいます。これが「冷凍焼け」の正体です。冷凍焼けした食材は、パサパサで食感が悪くなるだけでなく、空気に触れることで脂肪が酸化し、風味も著しく劣化します。
解決策
•空気を完全に遮断する: ラップで包む際は、空気が入らないようにぴったりと密着させます。さらにジッパー付き保存袋などに入れて二重に保護するのが効果的です。
•真空包装機を活用する: 最も確実な方法は、真空包装機を使用することです。真空パックは、乾燥と酸化を同時に防ぐことができる、冷凍保存における最強のパートナーです。
【失敗事例5】解凍方法を誤り、品質を台無しに
ありがちな失敗: 「急いでいるから」と、冷凍した食材を常温で放置したり、電子レンジの解凍機能を使ったりする。
なぜ失敗するのか: せっかく急速冷凍で細胞破壊を最小限に抑えても、解凍方法を間違えれば、解凍時に細胞が破壊され、大量のドリップが流出してしまいます。急激な温度変化は、ドリップを増やす最大の原因です。
解決策
•低温でゆっくり解凍する: 基本は、冷蔵庫内でゆっくり解凍するか、真空パックのまま氷水に浸けて解凍する「氷水解凍」です。これにより、内外の温度差を少なくし、ドリップの流出を最小限に抑えることができます。
•流水解凍: 急ぐ場合は、真空パックのまま流水に当てて解凍します。ただし、水の当てっぱなしはコストがかかるため注意が必要です。
•加熱調理: スープや煮込み料理に使う場合は、凍ったまま調理することも可能です。
詳しくは、解凍方法で変わる!急速冷凍食品の美味しい食べ方で解説しています。
失敗を防ぐための5つのチェックリスト
これまでの失敗事例を踏まえ、自社の運用を見直すためのチェックリストを作成しました。一つでも「いいえ」があれば、改善の余地があります。
| No. | チェック項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|---|
| 1 | 【温度管理】 熱いものを冷まさずに冷凍庫に入れていないか? | ☐ | ☐ |
| 2 | 【前処理】 食材の水分を拭き取り、適切な下処理(洗浄、ブランチング等)をしているか? | ☐ | ☐ |
| 3 | 【処理能力】 冷凍機の処理能力を超えて、食材を詰め込みすぎていないか? | ☐ | ☐ |
| 4 | 【包装】 空気を抜き、しっかりと密閉して包装しているか?(真空包装が理想) | ☐ | ☐ |
| 5 | 【解凍】 解凍時に、常温解凍や電子レンジ解凍をしていないか? | ☐ | ☐ |
まとめ
急速冷凍の失敗は、いくつかの基本的なルールを守るだけで、そのほとんどを防ぐことができます。
本記事で解説した5つの失敗パターンを再確認しましょう。
1.温度管理の誤解: 「設定温度」ではなく「凍結速度」が重要。
2.前処理の軽視: 水分、汚れ、酵素は品質劣化の元凶。
3.過剰な詰め込み: 冷気の循環を妨げ、凍結ムラを引き起こす。
4.不適切な包装: 乾燥と酸化による「冷凍焼け」の原因。
5.間違った解凍: 急激な温度変化はドリップを増やす。
これらの失敗は、裏を返せば、急速冷凍機の性能を最大限に引き出すための「成功の秘訣」でもあります。高価な設備投資を無駄にしないためにも、ぜひ一度、自社の運用フロー全体を見直してみてください。
「自社のやり方が正しいか、専門家に見てもらいたい」 「この食材の最適な冷凍方法が知りたい」
KOGASUNでは、そのようなお客様の声にお応えするため、無料の冷凍テストや導入後の運用サポートを充実させています。急速冷凍に関するお悩みがあれば、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。